週中の木曜日、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は、沖縄守り神であるシーサーの記念日だそうです。由来は、シー(4)サー(3)の語呂合わせだとか。なかなか面白い記念日ですね。
本日も、”バフェットの銘柄選択術”で学んだ分析方法を使って、企業分析を実践してみます。本日は、伊藤忠商事(銘柄コード:8001、以下同社と呼びます)です。バフェットは2020年に5大商社(三井物産、三菱商事、丸紅、住友商事、伊藤忠商事)の株式をそれぞれ7~8%程度購入しています。また、3月17日には、それぞれ9%程度の株式を追加購入しました。
分析に入る前に、バフェットの銘柄選択術の13項目を軽く要約します。13項目は企業分析と株価分析の2つのパートに分かれています。13項目すべて確認するのではなく、質問に対して”いいえ”の項目があった時点で分析を止めて、他のもっとよい企業を分析することが推奨されています。もし、13項目の具体的な内容を知りたい方は、ぜひ以前の記事(https://ted-lifeblog.com/books_buffet_check_13/)をご一読ください。また、分析はあくまで私見ですので、投資される際は自己責任でお願いいたします。
株価分析パート
Q10.その企業の株価は、相場全体の下落や景気後退、一時的な経営問題などのために下落しているか?
4/3の同社の株価は、6,632円でした。過去3年を通して株価は、3,500円台~8,166円で推移しています。そのため、少し高めの株価になります。そのため、回答は”はい”とします。経営問題などの記載は見当たりませんでした。最近の日経平均の下落を受けて、同社の株価は少し下がり初めています。
Q11.株式の益利回りと利益の予想成長率を計算し、国債利回りと比較せよ
同社の2023年のEPSは、546.1円です。これを2024年2月の10年もの国債利回り1.21%で割ると、国債に対する相対価値は、451円となります。これに対して、直近3年の実際の株価は、3,500円台~8,166の範囲にあり、仮に2023年12月30日に購入したとすると、7,832円となります。購入単価に対する直利を求めると、7.0%(451円/7,732円)。同社の過去10年のEPS成長率は年平均12.9%だから(昨日のQ5参照)、同社の株は、初年度直利が7.0%で、年平均12.9%ずつ、クーポンが成長する疑似債券と見ることができます。従って、この疑似債権と、利回り1.21%に固定されている国債のどちらに投資するかということになります。
Q12.株式を疑似債券と考え、期待収益率を計算せよ
株式を疑似債券とみなすと、債券と同じように期待収益率を計算できます。具体的には、以下の方法です。
1)Q6で計算した過去10年の平均ROEから、配当として支払われる部分(ROE*平均配当性向)を差し引いた純粋な株主資本の予想成長率を求める。
株主資本の予想成長率=過去10年の平均ROE*内部留保率(1-配当性指向)= 14.7%*(1-0.256)% = 10.96%
2)株主資本の予想成長率と直近の1株あたりの株主資本(BPS)から、10年後の予想BPSを計算する。
予想BPS=直近のBPS*(1+株主資本の予想成長率)^10 = 3,314.3円*(1+0.1096)^10 = 9,376円
3)予想BPSと平均ROEを掛けて予想EPS(Earning per share, 1株あたりの利益, 税引利益/発行済株式数)を計算する
予想EPS=予想BPS*平均ROE =9,376円*10.96% = 1,381円
4)予想EPSに過去10年間の平均PER(Price Earnings Ratio, 株価収益率, 株価/一株あたりの利益)を掛けて10年後の予想株価を求める
10年後の予想株価下限 = 予想EPS*過去10年間の最低PER = 1,381円*6.18倍 = 8,538円
10年後の予想株価上限 = 予想EPS*過去10年間の最高PER = 1,381円*9.11倍 = 12,582円
5)10年後の予想株価に今後10年分の予想配当金合計額を加えた値と、現在の株価から今後10年間の期待収益率を計算する。計算式は、期待収益率=(10年後の予想株価/現在の株価)^(1/10)-1 です。
税引前手取金額(下限)=10年後の予想株価の下限+今後10年分の予想配当金合計額= 8,538円+2,893円=11,428円
税引前手取金額(上限)=10年後の予想株価の上限+今後10年分の予想配当金合計額= 12,582円+2,893円=15,475円
税引前手取金額(下限)の期待収益率=(11,428円/7,832円)^(1/10)-1 = 3.85%
税引前手取金額(上限)の期待収益率=(15,475円/7,832円)^(1/10)-1 = 7.05%
Q13.過去のEPS成長率を元に計算する手法で、期待収益率を計算せよ
1)直近のEPSと10年前のEPSをもとに、過去の平均EPS成長率を出す。計算式は、過去の平均EPS成長率=(直近のEPS/10年前のEPS)^(1/10)-1
過去のEPS平均成長率=(546.1円/162.32円)^(1/10)-1 =12.9%
2)直近のEPSと過去10年間の平均EPS成長率に基づいて、10年後の予想EPSを計算する。計算式は、予想EPS=直近のEPS✕(1+過去の平均EPS成長率)^10である
同社のEPSが、過去10年間の成長率と同じ12.9%で今後も成長を続け、配当性向が25.6%で維持されるなら、2024年から2033年にかけてのEPSと配当の状況は、以下のように予想される。
年 予想EPS(円) 予想配当(円)
2023 546.1 166 *基準年
2024 616.54 157.83
2025 696.07 178.19
2026 785.85 201.18
2027 887.22 227.13
2028 1001.66 256.43
2029 1130.87 289.50
2030 1276.74 326.85
2031 1441.43 369.01
2032 1627.36 416.60
2033 1837.27 470.34
(2024年~2033年の配当合計は、約2,893円)
3)予想EPSに過去10年間の平均PERをかけて、10年後の予想株価を求める
10年後の予想株価下限 =2033年の予想EPS*過去10年間の最低PER = 1837.27円*6.18倍 = 11,354円
10年後の予想株価上限 = 2033年の予想EPS*過去10年間の最高PER = 1837.27円*9.11倍 = 16,738円
4)10年後の予想株価と現在の株価から今後10年間の期待収益率を計算する。計算式は、期待収益率=(10年後の予想株価/現在の株価)^(1/10)-1 である。
税引前手取金額(下限)=10年後の予想株価の下限+今後10年分の予想配当金合計額
=11,354+2,893=14,247円
税引前手取金額(上限)=10年後の予想株価の上限+今後10年分の予想配当金合計額=16,738+2,893=19,631円
税引前手取金額(下限)の期待収益率=(14,247円/7,832円)^(1/10)-1 = 6.17%
税引前手取金額(上限)の期待収益率=(19,631円/7,832円)^(1/10)-1 = 9.62%
株価分析のまとめ
仮に、2023年12月30日時点の価格7,832円で同社の株を1株購入したとします。同社の株を、疑似債券としてみると、初年度の直利は7.0%、クーポンの成長率は、12.9%となります。これを元に同社の株を10年間保有する場合の期待収益率を計算すると、税引前で3.85%(Q12のPER6.18倍のケース)から、9.62%(Q13のPER9.11倍のケース)の範囲という結果が得られます。つまり、10年保有した場合の税引前手取り金額の範囲は、11,428円~19,631円となります。
以上が、株価分析パートでした。いかがでしょうか?
結果評価
この分析がどの程度正しいかは、最終的には2033年まで待ってみないと難しいです。しかし、2024年の同社の決算短信から2024年のみ数字で検証したのが以下の表です。
年 予想EPS($) 実績EPS($) 予想に対する誤差 予想配当(円) 実績予想配当(円) 予想に対する誤差
2023 546.10 546.10 0.0% 166 166 0.0%
2024 616.54 553 -10.3% 158 160 1.4%
2024年の実績EPSは546.1円で、予想よりも-10.3%。配当金は160円で、予想よりも1.43%でした。配当性向は28.9%で少しアップでした。
さて、私個人としては、同社は消費者独占企業とするには少し迷うところがあります。理由は、他の商社(三井物産、三菱商事、丸紅)と同じように、金属資源がメインとなっており、競争優位性が読めなかったためです。しかし、金属資源の次に多いのが、機械である点は他の商社とは異なります。引き続き、ウォッチリストに入れて見ていきます。
最後まで読んで読んでいただき、本当にございます。今日も良い一日をお過ごしください!

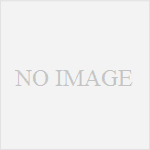
コメント