皆さん、こんばんは!
天気予報によると、今週末は、冬将軍が猛威を振るうようですね。日本海側だけではなく、太平洋側でも一部積雪のおそれがありそうです。積雪による怪我や事故にご注意下さい。
さて、本日は、”バフェットの銘柄選択術”の中から、バフェット流投資のためのワークーシートに記載された13のチェック項目をご紹介します。同書籍では、13項目全て確認するのではなく、1つでも満たせない項目があれば、それ以上その企業を分析せず、投資を見送るべきとしています。特に、選択の余地がない商品の魅力や金のかからないブランドの強み等を持つ消費者独占企業以外は、投資をせず、さっさと次の企業を分析しなさいとの態度が徹底されています。
バフェット流投資のためのワークーシートは、企業分析と株価分析の2つのパートに分かれています。各ポイントは、ほぼ質問形式で書かれています。
企業分析パートは、決算書、有価証券報告書、統合報告書の記載内容からわかる企業の事業内容や業績を中心に分析することが主目的になります。株価分析パートでは、企業分析パートの内容を元に、10年後の予想株価の算出、期待収益率を分析して、最終的に投資するかしないのかを判断します。
それでは、まずは企業分析パートのポイントを紹介していきます。
企業分析パート
Q1.その企業は消費者独占力を持っているか?
もしこの質問の解答が「はい」であれば、7歳の子どもでもわかるような簡単な言葉で説明せよ。
Q2.その企業の事業内容を理解しているか?
事業内容を説明できないようなら投資は見送るべき。
Q3.その企業の製品・サービスは20年後も陳腐化していないか?
あなたが選んだ企業の製品・サービスが20年後も陳腐化していないと考える理由や根拠を述べよ。
Q4.その企業はコングロマリットか?
もし「はい」なら、それが競争力が不足したコモディティ型ビジネスに多角化した結果なのか、消費者独占力のある他の企業を買収・統合した結果なのかを調べよ。もし後者の可能性が高いなら、分析を継続せよ。なお、コングロマリットを分析する場合、個々の事業を消費者独占型か、コモディティ型にわけて、リストを作ってみるとよい。その上で、企業が両者のどちらの方向にビジネスを展開していくか、確認しなくてはならない。
Q5. その企業の1株あたりの利益(EPS)は、安定成長しているか?
過去10年のEPSを調べて、その年平均成長率を計算せよ。もし、答えが「いいえ」なら、利益の落ち込みが一時的なものなのか、そうでないのか確認せよ。一時的な落ち込みでないなら、次の企業の分析に移るべし。
Q6.その企業は安定的に高い株主資本利益率(ROE)を上げているのか?
過去10年間のROEを調べて、平均ROEを計算せよ。ひとつの目安としては、平均ROEが15%以上である。
Q7. その企業は、強固な財務基盤を有しているか?
消費者独占企業は、利益が高く、負債はなしか、あっても極めて少ない。そのため、長期負債を税引後利益で割って、長期負債を税引後利益で返済するには何年かかるか、計算せよ。
Q8.その企業は自社株買いに積極的か?
企業が自社株買いすると、既にその企業の株を持っている投資家は、買い増ししなくても持ち株比率を高めることができる。自社株買いについての具体的な調査方法は、10年前の発行済株数から、今期の発行済株数を引くと、過去10年間に自社株買いした株数を計算できる。発行株数が減少している企業を探すべき。
Q9.その企業の製品・サービス価格の上昇はインフレ率を上回っているか?
もし製品・サービスの価格が20年前と変わらないなら、その企業はコモディティ企業である可能性が高い。具体的には、過去20年間における製品・サービス価格の年間平均上昇率を計算せよ。
企業分析パートは、以上です。いかがでしたでしょうか?有価証券報告書や統合報告書を読んでも、確認することが少ない点だなと感じました。さて、次は株価分析パートです。
株価分析パート
Q10.その企業の株価は、相場全体の下落や景気後退、一時的な経営問題などのために下落しているか?
もし「はい」なら絶好の買い場である。消費者独占力のある企業を割安な水準で買うためには、個別の悪材料や市場の短期な下落を利用して、安く買うことが大切である。
Q11.株式の益利回りと利益の予想成長率を計算し、国債利回りと比較せよ
仮に株式を債権と考えると、今期のEPSを現在の株価で割った利回り(益利回り)は、投資に対する直利と捉えられる。また、Q5で求めたEPSの成長率は、債権のクーポンの期待成長率とみなすことができる。もしこの益利回りとEPSの成長率の合計が、国債利回りよりも低ければ、その企業の株価は割高だと判断できる。
Q12.株式を疑似債権と考え、期待収益率を計算せよ
株式を疑似債権とみなすと、債権と同じように期待収益率を計算できる。具体的には、以下の方法である。
1)Q6で計算した過去10年の平均ROEから、配当として支払われる部分(ROE✕平均配当性向)を差し引いた純粋な株主資本の予想成長率を求める。
2)株主資本の予想成長率と直近の1株あたりの株主資本(BPS)から、10年後の予想BPSを計算する。計算式は、予想BPS=直近のBPS✕(1+株主資本の予想成長率)^10を使う
3)予想BPSと平均ROEを掛けて予想EPS(Earning per share, 1株あたりの利益, 税引利益/発行済株式数)を計算する
4)予想EPSに過去10年間の平均PER(Price Earnings Ratio, 株価収益率, 株価/一株あたりの利益)を掛けて10年後の予想株価を求める
5)10年後の予想株価と現在の株価から今後10年間の期待収益率を計算する。計算式は、期待収益率=(10年後の予想株価/現在の株価)^(1/10)-1 である。
Q13.過去のEPS成長率を元に計算する手法で、期待収益率を計算せよ
1)直近のEPSと10年前のEPSをもとに、過去の平均EPS成長率を出す。計算式は、過去の平均EPS成長率=(直近のEPS/10年前のEPS)^(1/10)-1
2)直近のEPSと過去10年間の平均EPS成長率に基づいて、10年後の予想EPSを計算する。計算式は、予想EPS=直近のEPS✕(1+過去の平均EPS成長率)^10である
3)予想EPSに過去10年間の平均PERをかけて、10年後の予想株価を求める
4)10年後の予想株価と現在の株価から今後10年間の期待収益率を計算する。計算式は、期待収益率=(10年後の予想株価/現在の株価)^(1/10)-1 である。
以上が、株価分析パートでした。いかがでしょうか?
計算式だけだと理解しづらい部分はありますが、書籍では、ケーススタディとしてガネット、フレディ・マック、マクドナルドを例に計算式と解説が書かれています。
株価分析パートまで完了したら、最後に投資するか否かの判断基準として、同書籍では以下を推奨しています。分析対象の企業が消費者独占力を持たなければ、そもそも投資を検討するに値しない。消費者独占力があり、かつ、株価分析の結果、株価が割安ならば投資すべき。割安でないなら、相場全体の下落、景気後退、一時的な経営問題で、株価が下がるまで投資は控えるべし。
個人的な印象としては、なかなか最後の13項目までOKとなる企業はほとんどない気がしています。それほど消費者独占力がある企業は希少であるという事なのかもしれません。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

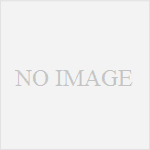

コメント